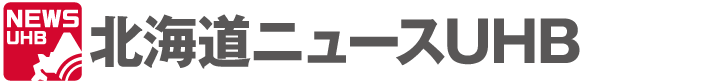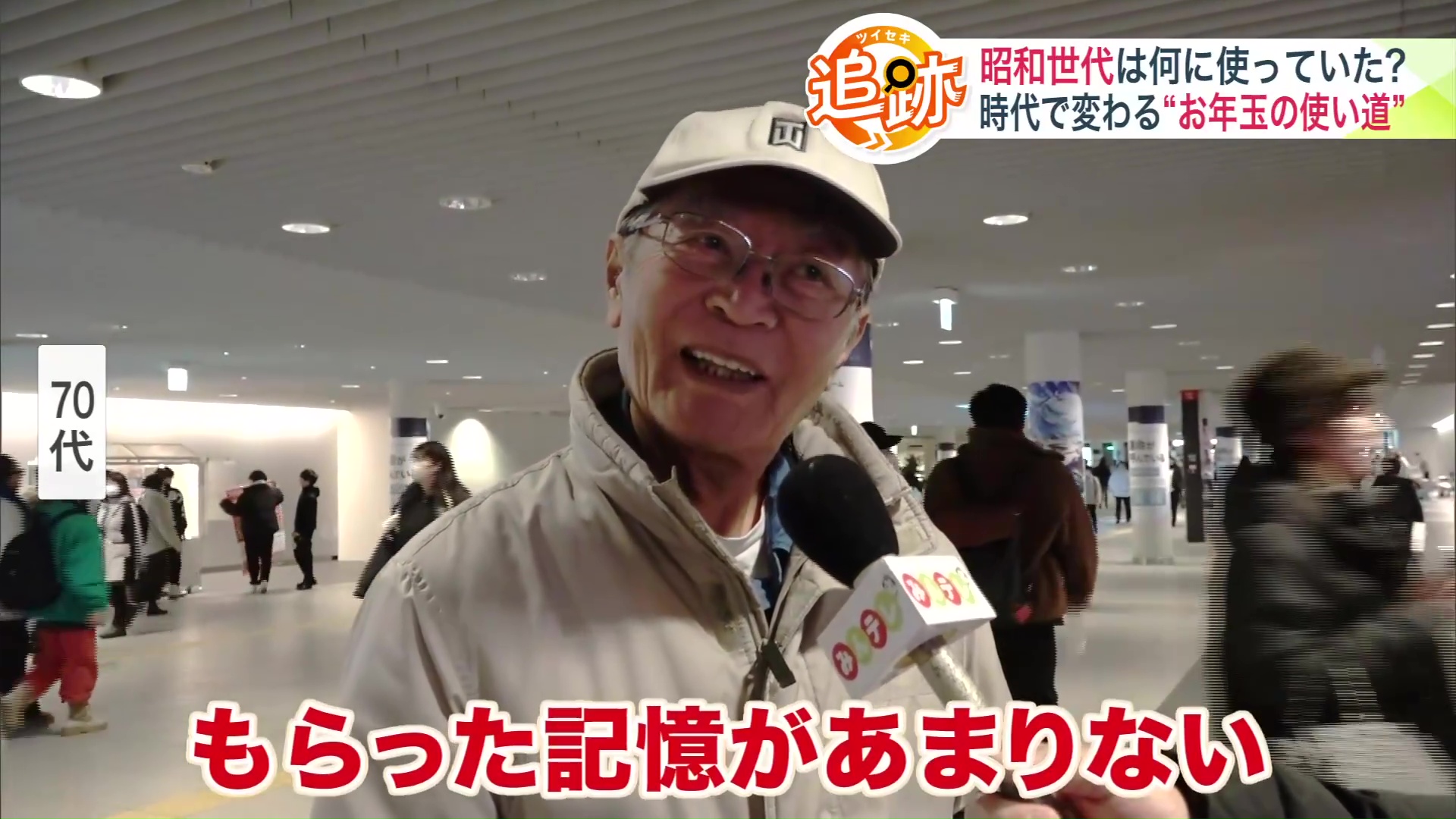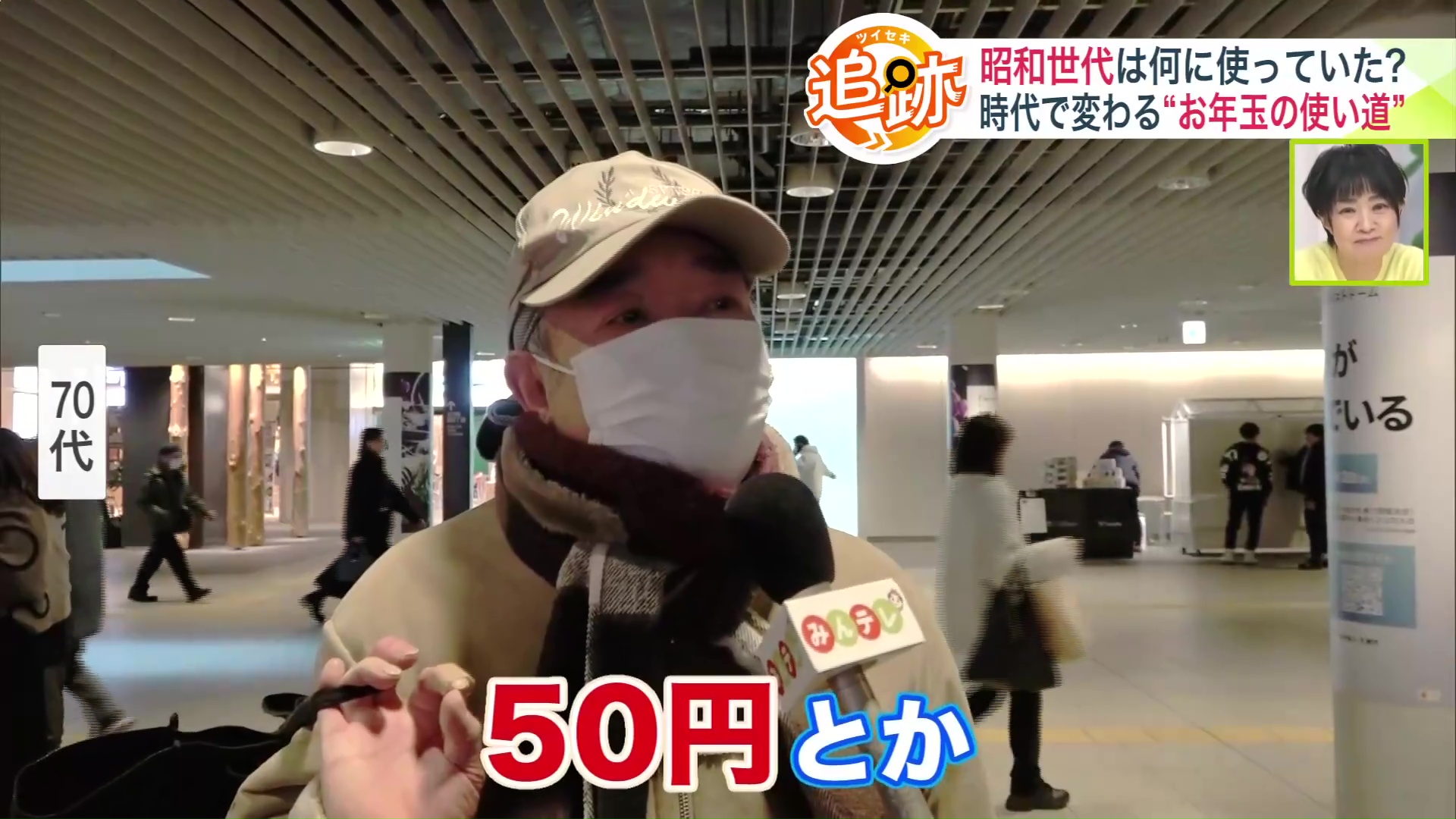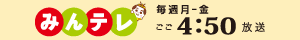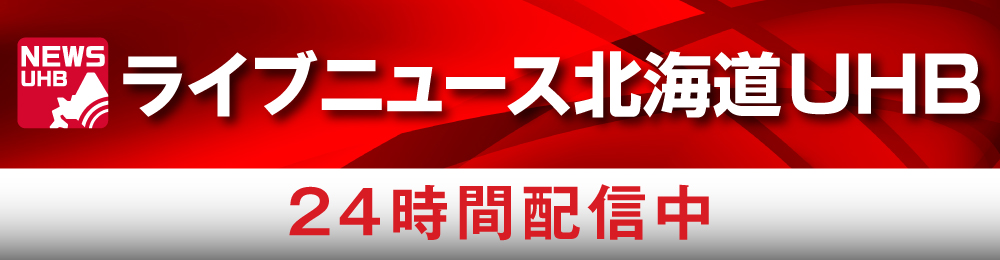【令和のお年玉事情】小中学生でも1~2万円!? いくらあげた?もらった?"推し活"やゲーム課金 積み立てNISAで「増やす」家庭も
「小学生と中学生は個数を決めて例えば、全部で7個もらったら、後ろに並べて高校生は全部あげるけど小学生なら2つとか3つとか選ばせたお年玉をあげる」(父親)
親族からもらったポチ袋を一列に並べ、小中学生は決められた個数を見ないで選びます。
そこに入っていたお金をその年のお年玉としてもらい、残りは親が管理。
お年玉の金額は統一されていないので選んだポチ袋によってもらえる額が変わるという斬新なシステム!
「今年は3万円くらい最高額が1万円、最低額が3000円だった。一番下の3000円も引いちゃったから、全部いいのがよかった」(中学1年生/ポチ袋×4 計3万円)
「お手伝い頑張ったとか、テストで結果がよかったら+ポチ袋1個今年は頑張ったから4つにしようとか」(父親)
「年末調整的な」(母親)
Qじゃあ今年は頑張ったってことでプラス1つ?
「もうちょっといけたなって思いました」(中学1年生)
「全部ほしいという欲はあるけど金遣いが荒いから逆にくじ引きの方がありがたい」(小学5年生)
一方、以前のお年玉事情は。
Q子どものころお年玉をもらっていた?
「もらった記憶がない、そこそこ大きくなってからだろうか、たぶん小学校の時代はもらっていない」(70代)
「高校生になって、もらった記憶がない。それだけの余裕がなかった」(80代)
日本では、もともとお年玉はお金ではなく、年神様を迎えるためにお供えされた丸い鏡餅のことを指していました。
それが高度経済成長期が始まった1955年ごろから、お金をあげる文化に変わっていったといいます。
しかし、当時は戦後で金銭面に余裕がない家庭も多く、お年玉をもらっていない人も多かったようです。
もらっていたとしても金額は。
「玉だね札ではなかった。50円とか貯金するとか、そんなのはなかった」(70代)