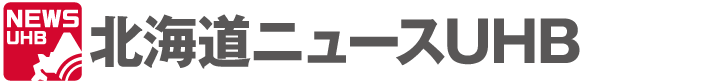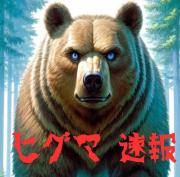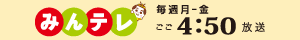“総延長100キロ”ヒグマ侵入を防ぐ「電気柵の長城」構想―住宅街に出没し4人負傷…3年たち模索し始めた“すみ分け”
小谷さんは、25年前から過疎化で荒廃した地区への移住を全国から促し、今では約50世帯が暮らす。人が住むことで、東区のヒグマが通ったような、身を隠しながら移動できる草地が整備される。
ヒグマが増えたから減らすのではなく、近づかなくすることが共生には必要だと小谷さんは考えている。「里山が荒廃しているのは北海道だけではない。一日も早く実用化し、全国にも発信したい」。小谷さんは熱っぽく語る。
100キロを敷設するとなると、総額は10億円に膨らむ。しかし、電気柵の敷設により、高騰する輸入飼料に頼らず放牧で育てることができたため、3~5割のコストカットに成功した実績もある。2021年、小谷さんは野生動物と経済活動の関係を模索したい北海道大学農学部とともに共同プロジェクトを始動させた。
電気柵導入で目撃数激減の事例 課題も山積
ヒグマが頻繁に出没する知床半島の斜里町では、2006年にクマ対策でウトロ地区を取り囲むように4キロの電気柵を導入、2007年に稼働した。49件だったクマ目撃数は、稼働後1年で5件に激減した。
「ヒグマが出没すると電話を受けて出動するが、その回数もだいぶ減った。シカやヒグマの侵入は確実に抑えられている」(知床財団担当者)
その後、2キロ延伸したが、課題も浮き彫りになっている。費用の3000万円は町が負担。一部を北海道が補助した。草がワイヤーに触れると、漏電し効果がない。小まめな草刈りが必要で、電気代を含めて年間170万円の維持費がかかっている。
課題を解決するため、小谷さんは北海道大学農学部との共同研究をすすめ、環境省の研究事業としての認可を目指す。10月18日、事業計画を提出した。
「国への申請には5年くらいかかる。まずは当別町で町有林の活用も含め、10~20キロの緩衝帯の整備。うまくいったら5倍10倍くらいの距離に伸ばしたい」(小谷さん)
単なる防壁ではなく、経済力を持った緩衝帯を創造する。実用化は25年先の2050年。ヒグマとの共生の道に一歩踏み出すべく、息の長い活動は始まったばかりだ。