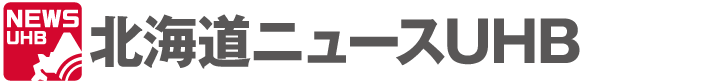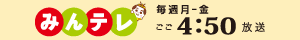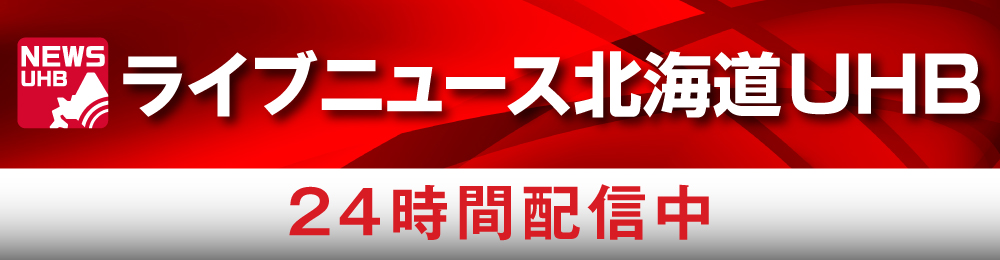「個人のヒグマ対策に最適」持ち運べる電気柵―“野生動物”を傷つけない…市街地で出没相次ぐ中 北海道の企業が開発
ヒグマの出没が市街地で相次ぎ市民生活に深刻な影響を及ぼす中、北海道の企業が開発した"持ち運べる電気柵"が注目されています。大規模な農地などで使われることが多かった電気柵を個人でも手軽に扱えるようにしたツール。キャンプや家庭菜園など、より身近な場面でのヒグマ対策として使われ始めています。
乾電池2本で動く"心理柵" 10分で設置も可能
ポータブル電気柵は山林レンタル事業を展開する「レンタリン」(道新サービスセンター運営)と、野生動物用のわなや電気柵の製造・販売会社「ファームエイジ」(本社・北海道石狩市)が共同開発しました。
1985年の創業以来、エゾシカ対策などで実績を重ね、ヒグマ対策の電気柵は知床の遊歩道など道内各地で導入されています。
商品名は「デンキリン」。手軽に扱え、単一乾電池2本だけで最大約35日間連続使用できます。
特別な工具も不要です。実際に利用した人からは「慣れたら50メートルの距離を10分程度で設置できた」「これがあると安心感がある」との声も聞かれます。
「ここは危険な場所だ」 学習させる“心理柵”
電気柵は、物理的に動物の侵入を防ぐ柵とは異なり、触れた動物に電気ショックを与えて「ここは危険な場所だ」と学習させる"心理柵"です。
電気ショックは、人が触れても強めの静電気が流れる程度の衝撃。動物を傷つけることなく危険を学習させることができるといいます。特に、障害物をよじ登る能力が高いヒグマに対しては、この心理的なバリアが有効とされています。
行政が認める効果 「個人の自衛」ニーズに応える
電気柵は行政もクマ対策のひとつとして、効果を認めています。
北海道が策定したヒグマ管理計画では、「ヒグマの農地への侵入防止に高い効果がある」として電気柵の導入促進を明記。総務省が公表した「ヒグマの人里への出没対策等に関する実態調査」でも、出没予防対策として電気柵の有効性が示されています。
ただ、従来の電気柵は大規模な設置を前提としたものが多く、個人がキャンプや山仕事、自宅の家庭菜園を守るために導入するには、ハードルが高いのが実情でした。
開発されたポータブル電気柵は、「個人の自衛」のニーズに応えるため、商品化されました。
電気柵の必要性 「共生のために正しく境界を」
専門的な用途から日常的な安心の確保まで、幅広い場面で活用され始めています。
「仕事で山に入ることが多いので、テントの周りだけ囲って使っている」
「自分が借りている山の区画に常時設置している。今のところクマが出る地域ではないが安心感がある」(いずれも利用者)
ファームエイジは「ヒトと動物がそれぞれ適切な場所で暮らし、共生できる社会を目指しています。そのためにも正しく境界を設けることが重要」と必要性を説いています。
"持ち運べる電気柵"は、人とヒグマの間に適切な距離を保ち、不幸な事故を防ぐための新たな選択肢となりそうです。