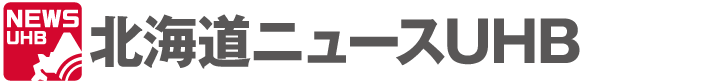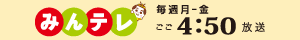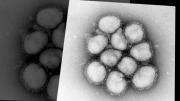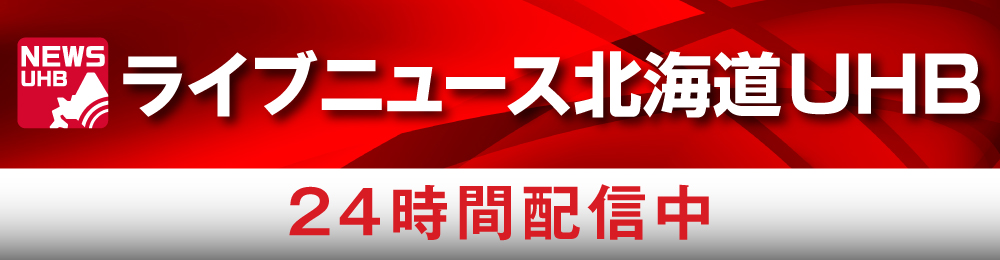注目される「インクルーシブ教育」重度の知的障がいと自閉症がある生徒、戸惑いながらも理解を深めていくクラスメイトの成長の記録…卒業後も続く絆―障がいで子どもを分けずともに学ぶ意義とは
障がいのあるなしに関わらず、ともに学ぶ「インクルーシブ教育」への関心が高まっています。
ともに学ぶ現場を見つめました。
2024年10月、旭川市。
少し緊張した様子の平田和毅さん、みんなはカズと呼びます。
カズを囲んでいるのは、中学の同級生です。
重度の知的障がいと自閉症があるカズ。
中学の3年間、普通学級で仲間とともに学びました。
障がいのある、なしに関わらずともに学ぶ"インクルーシブ教育"について考える集会に登壇しました。
「平田和毅です。よろしくお願いします」
「カズって面白いんだ、カズってこうなんだって知るきっかけがたくさんあって、一緒のクラスになって知ることができた」
一緒に過ごした時間は、子どもたちに何をもたらしたのでしょうか。
5歳のころ、カズは障がいのある子を対象にした幼稚園と、地域の幼稚園の両方に通っていました。
ある日、両親はカズがとった行動に衝撃を受けました。
「絵カードでその日に行く幼稚園を指し示して、きょうはこっち、あしたはあっちという形でやっていたが(和毅が)地域の幼稚園の絵カードを私たちの方に持ってきて、こっちの方に行きたいんだと(意思を示した)」(和毅さんの父親)
地域の幼稚園に通ううち表情に変化が出てきました。
「すごく楽しそうでした」(和毅さんの父親)
小学校は特別支援学級に通いましたが、両親は中学校では普通学級で学ぶことで地域との交流を持ってほしいと考えました。
しかし、入学前に教育委員会からはこう伝えられました。
「和毅くんのような障がい特性のある子は、配慮を提供できない。彼のような特性のある子は、特別支援学校に行って、しっかりとした個別のニーズに基づいた支援、もしくは指導を受けることが大切だと」(和毅さんの父親)
事実、戸惑いは学校側にもありました。
担任を務めることになる曽我部昌広さんです。
「入ってくる前は会議も何度かあって。ムリだろうとか大変なことになるという否定的な意見が大半だったんですけど。(自分も)どうなるのかなと思っていたが、同じ生徒としてやっていこうという気持ちでした」(担任の曽我部先生)
初めは行動に戸惑ったものの、クラスメイトは次第に理解できるようになっていきました。
「ペンを机に並べたり、授業中に立ち上がったり、歌いだしたりとか。通常では起こらないことをどうするか考えることが多くなった。一緒にいる中で、障がい特性でできないことや、カズでもできることなんだな、など毎日一緒に生活する中で見極めていった」(担任の曽我部先生)