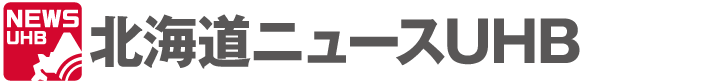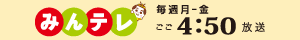子どものSOSに気づく― 夏休み明けに増加する精神的苦痛 どう解決する? いじめによる "悲劇" を繰り返さないために…"小さなサイン"を見逃さないで
8月26日、北海道では多くの小中学校で始業式が行われました。
実は、夏休み明けは精神的に追い込まれる子どもが増えるとされています。
どうすれば子どもを守ることができるのでしょうか。
「夏休みが長かったから去年より早く学校に行きたい気持ちが強くなった」(小学4年生)
「長いと結構できることも多くて楽しかった。プールに行ったり北見などちょっと遠くへ行ったり。ちょっと夏休みが終わっちゃうのは寂しい」(小学6年生)
長く楽しかった夏休みを終え、北海道内の多くの小中学校で迎えた始業式。
一方、夏休み明けは悩みを抱えた子どもが増えるのも事実です。
夏休み明けは精神的に追い込まれる子どもも…
厚労省の調査では2022年に自殺した人は前年から874人増えて2万1881人。
そのうち小中高校生は過去最多514人にのぼりました。
内閣府の日別での分析では、本州が夏休み明けとなる9月1日が、命を絶つ子どもが最も多くなっています。
悲劇を起こさないために―
「(Q:休み明けは憂鬱?)私の方が憂鬱ですね。やっぱりね気が重かったりしますよね。それは大人もあるので気持ちはわかります」(保護者)
なぜ夏休みあけに集中しているのでしょうか?
「“学校の中に問題”が何かある。それが解決できていない表れ。かなりの割合で“いじめ”が存在していると感じる。夏休み半ばとか、後半からカウントダウンのように緊張感が高まる」(ジェントルハートプロジェクト 小森 美登里 理事)
子どもをいじめなどから守る活動をする小森美登里さん。
小森さん自身も26年前、一人娘の香澄さん(当時15)をいじめで失いました。
「我が子が経験した苦しみや娘の死によって感じたことを無駄にしたくない」(小森さん)
悲劇を起こさないため、教育現場ではどのような対策をしているのでしょうか。
札幌市北区の篠路西中学校では。
「休み中は『学習会』などがありその時に(生徒の)様子を見る場面を設けたり、休み明けは質問、アンケートを設けて心と体の状態を自分で書いてもらう。心配な内容が書かれていたらすぐに話を聞いてケアをしていく」(篠路西中学校 丹保祐太さん)